この記事を多くの人に読んでもらいたい!!そう思ったら『人気ブログランキング』押してください
「美味い」、そして「酔える」それだけでいいのだ。 ― 2008年01月06日 01時14分01秒
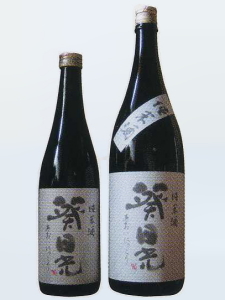
皆様、明けましておめでとうございます。
私は酒好きです。そしてざるです。
というか「人と飲んでいると酔えない」という、悲しい体質な訳です。
(酔えないというか「酔っても意識を失わない」という悲しい体質です)
が、家で一人で飲んでいる時は別。
好き勝手に酔っても、誰に迷惑がかかるわけじゃないので簡単に酔えます。
……人の目があると自制が激しいというだけなのですが。
ただ、やはりお酒に薀蓄はいらないでしょう。
必要なのは「美味い」と「気持ちよく酔える」という2点だけ。
他にくだらない言葉はいらないと思います。
さて、そんな私が今飲んでいるのが、これ。
仙禽酒造
純米『葵日光』
高い酒も美味いのですが、安い酒でも楽しむ事ができます。
地酒の純米酒は意外と隠れた銘酒があります。
葵日光(純米酒の安い方)も、安いのですが、意外と呑める酒だと思います。
このブログを見ている酔狂な人にも酔える酒があると思います。
「美味い」と感じ「酔える」
それだけでいいとおもいませんか?
……酔っているから、書いている内容ぐだぐだ。
私は酒好きです。そしてざるです。
というか「人と飲んでいると酔えない」という、悲しい体質な訳です。
(酔えないというか「酔っても意識を失わない」という悲しい体質です)
が、家で一人で飲んでいる時は別。
好き勝手に酔っても、誰に迷惑がかかるわけじゃないので簡単に酔えます。
……人の目があると自制が激しいというだけなのですが。
ただ、やはりお酒に薀蓄はいらないでしょう。
必要なのは「美味い」と「気持ちよく酔える」という2点だけ。
他にくだらない言葉はいらないと思います。
さて、そんな私が今飲んでいるのが、これ。
仙禽酒造
純米『葵日光』
高い酒も美味いのですが、安い酒でも楽しむ事ができます。
地酒の純米酒は意外と隠れた銘酒があります。
葵日光(純米酒の安い方)も、安いのですが、意外と呑める酒だと思います。
このブログを見ている酔狂な人にも酔える酒があると思います。
「美味い」と感じ「酔える」
それだけでいいとおもいませんか?
……酔っているから、書いている内容ぐだぐだ。
グーグルの脅威 ― 2008年01月09日 16時47分33秒
新パワーゲーム 6 グーグル脅威論 浮上(読売新聞 2008.1.9)
~ グーグルがその検索能力を使い、政府の情報検索を手伝っていたのだが、
いつのまにかメールや検索内容などの個人情報を国土安全保障省に提供していた。 ~
アメリカ コリードクトロウ氏の「グーグルが邪悪になったら」というSFだそうだ。
まだ私自身、読んだ事が無いが面白そうな話だと思う。
ただ、実際にはまだそのような事はないだろう。
しかし、彼らの検索が今、公明正大であっても、今後も公明正大である補償はない。
新聞にも書かれているようにグーグルの企業理念「邪悪にならない」という理念は非常に尊いものだと思う。だが「組織が強大化すれば変質する危険は常にある」という主張も正しいと思う。
実際、ネットでの検索についても、検索した後、閲覧するのは上位10リンク程度か1ページ目にのったサイトまでというのが一般的だろう。
そのため、各企業などはSEO対策などを行って検索ランキングが上位になるように修正しているのはよく聞く話だ。
だが、ここに仮に検索エンジンに何らかのフィルターをかけて、1ページ目に検索されるサイトを偏向させることができればどうなるだろう?
ある一定の傾向の意見のみを優位に導くことができれば、容易に大衆の意見を導く事が可能なのではないだろうか?
これをうがった見方だと感じる人も多いかもしれない。
しかし、私はここである事件が思い出されてならない。
それはごく最近、昨年の10月に起きた事件だ。
ある画像について検索しても、YahooおよびGoogleでは一切表示されなくなったという事件。その画像自体は日本中のサイトにあふれているにも関わらず、また権利者が削除要請をしたわけでもなく、また公序良俗に反する画像でもない「ただの普通の画像」にも関わらず、Yahoo、googleでは0件とされたという極めて問題のある事件だ。
そう「初音ミク画像消失事件」といわれる事件だ。
まあ、これはYahooとGoogleでは「意図的な削除は行っていない」というコメントが出ているし、私も「日本語」(初音ミク)を検索ワードとした時、システム上の問題からヒット条件から外された可能性が高いのではないかと考えている。
だが、これを簡単な技術的問題と片付ける事だと無視することは、私にはできない。
なぜなら、このように技術的なミスであったとしても、「検索エンジンは簡単にネット上での存在を否定する事ができる」という事を証明した事件だからだ。
元々、「検索」とは「情報を取捨選択し抽出する」行為にすぎない。
ならば、どの情報を抽出し提供するか否かについて、その選択権は「情報提供者」にしかなく、情報を受け取る側に「情報提供者が的確な情報を提供させる」権限はない。
だから、今回の検索についていえば、「間違っている」ことを指摘できたとしても、googleやyahooに「そのような検索をするな」と命ずることはできない。
このような関係から、情報を受ける側は、情報提供者との関係で常に「弱者」の地位に立たざるを得ないというのが常に前提となる。
そのため、本来、提供された情報が正確かどうか確認するために情報源をいくつも持っている事が、情報収集をする上での基本として要求されている。
しかしながら、今、このブログを読まれている人はどうだろうか?
今、ほとんどの情報源を「ネット」に頼っていないだろうか?
ネットの検索エンジンを使って「情報源サイトの抽出」を行っていないだろうか?
またWikipediaなどに頼っていないだろうか?
もし、一つの検索エンジンを使っていたり一つの情報集積サイトに頼っているのであればそれはとても危険だと思う。
「複数サイトを閲覧しているから大丈夫」と主張する事もできるかもしれない。
だけど、その複数サイトを抽出する情報源が1箇所しかない時、今まで書いた記事を読んで、それでも、その抽出サイトが「間違いなく公明正大に検索した」と胸を張っていえるだろうか。
実際、「Google八分」という現象がまれに発生している事も事実だ。
今はそれが「有害サイト」に多く見られる傾向にあるから安心していられるのかもしれない。だが、その方向が自分に向かってきた時、自分は大丈夫だと胸を張っていえるだけの力を自分は持っているのだろうか。
この点について、自分を含めネットに頼っている人は考え直す必要があるのかもしれない。
少なくとも情報源は複数持つ・情報ツールも複数持つ。
これが情報収集の基本であり、それは今でも十分必要な、というより今だからこそ十分気をつけて考えなければいけないことなのではないだろうか。
※ 余談だが、私が所属する千葉県行政書士会でも、『会でネットや一般からの情報を集約し会員に提供しよう』などの理由で会長が安易な思いつきで「業務情報特別委員会」という諮問機関を設置した。
だが、この特別委員会も「情報を集約し提供する」という事の本質的な注意点についてはまったく考慮せずに「会員のために情報を集約し提供することはいいサービスだ」という点のみで安易に考えていたので、委員だった私は、会長の意向に思いっきり冷水をぶっ掛ける行為としてその他の諮問事項もあわせ個人的見解を出して真っ向否定したという事実があったりする。
今回、参考までに書いた個人的見解から情報集約についての危険性などについてまとめた部分を抜粋してアップしておく。
抜粋:「情報ソースを一本に絞ることの危険性について」
http://www.aa.alles.or.jp/~g-lawyer/column/2008.html
~ グーグルがその検索能力を使い、政府の情報検索を手伝っていたのだが、
いつのまにかメールや検索内容などの個人情報を国土安全保障省に提供していた。 ~
アメリカ コリードクトロウ氏の「グーグルが邪悪になったら」というSFだそうだ。
まだ私自身、読んだ事が無いが面白そうな話だと思う。
ただ、実際にはまだそのような事はないだろう。
しかし、彼らの検索が今、公明正大であっても、今後も公明正大である補償はない。
新聞にも書かれているようにグーグルの企業理念「邪悪にならない」という理念は非常に尊いものだと思う。だが「組織が強大化すれば変質する危険は常にある」という主張も正しいと思う。
実際、ネットでの検索についても、検索した後、閲覧するのは上位10リンク程度か1ページ目にのったサイトまでというのが一般的だろう。
そのため、各企業などはSEO対策などを行って検索ランキングが上位になるように修正しているのはよく聞く話だ。
だが、ここに仮に検索エンジンに何らかのフィルターをかけて、1ページ目に検索されるサイトを偏向させることができればどうなるだろう?
ある一定の傾向の意見のみを優位に導くことができれば、容易に大衆の意見を導く事が可能なのではないだろうか?
これをうがった見方だと感じる人も多いかもしれない。
しかし、私はここである事件が思い出されてならない。
それはごく最近、昨年の10月に起きた事件だ。
ある画像について検索しても、YahooおよびGoogleでは一切表示されなくなったという事件。その画像自体は日本中のサイトにあふれているにも関わらず、また権利者が削除要請をしたわけでもなく、また公序良俗に反する画像でもない「ただの普通の画像」にも関わらず、Yahoo、googleでは0件とされたという極めて問題のある事件だ。
そう「初音ミク画像消失事件」といわれる事件だ。
まあ、これはYahooとGoogleでは「意図的な削除は行っていない」というコメントが出ているし、私も「日本語」(初音ミク)を検索ワードとした時、システム上の問題からヒット条件から外された可能性が高いのではないかと考えている。
だが、これを簡単な技術的問題と片付ける事だと無視することは、私にはできない。
なぜなら、このように技術的なミスであったとしても、「検索エンジンは簡単にネット上での存在を否定する事ができる」という事を証明した事件だからだ。
元々、「検索」とは「情報を取捨選択し抽出する」行為にすぎない。
ならば、どの情報を抽出し提供するか否かについて、その選択権は「情報提供者」にしかなく、情報を受け取る側に「情報提供者が的確な情報を提供させる」権限はない。
だから、今回の検索についていえば、「間違っている」ことを指摘できたとしても、googleやyahooに「そのような検索をするな」と命ずることはできない。
このような関係から、情報を受ける側は、情報提供者との関係で常に「弱者」の地位に立たざるを得ないというのが常に前提となる。
そのため、本来、提供された情報が正確かどうか確認するために情報源をいくつも持っている事が、情報収集をする上での基本として要求されている。
しかしながら、今、このブログを読まれている人はどうだろうか?
今、ほとんどの情報源を「ネット」に頼っていないだろうか?
ネットの検索エンジンを使って「情報源サイトの抽出」を行っていないだろうか?
またWikipediaなどに頼っていないだろうか?
もし、一つの検索エンジンを使っていたり一つの情報集積サイトに頼っているのであればそれはとても危険だと思う。
「複数サイトを閲覧しているから大丈夫」と主張する事もできるかもしれない。
だけど、その複数サイトを抽出する情報源が1箇所しかない時、今まで書いた記事を読んで、それでも、その抽出サイトが「間違いなく公明正大に検索した」と胸を張っていえるだろうか。
実際、「Google八分」という現象がまれに発生している事も事実だ。
今はそれが「有害サイト」に多く見られる傾向にあるから安心していられるのかもしれない。だが、その方向が自分に向かってきた時、自分は大丈夫だと胸を張っていえるだけの力を自分は持っているのだろうか。
この点について、自分を含めネットに頼っている人は考え直す必要があるのかもしれない。
少なくとも情報源は複数持つ・情報ツールも複数持つ。
これが情報収集の基本であり、それは今でも十分必要な、というより今だからこそ十分気をつけて考えなければいけないことなのではないだろうか。
※ 余談だが、私が所属する千葉県行政書士会でも、『会でネットや一般からの情報を集約し会員に提供しよう』などの理由で会長が安易な思いつきで「業務情報特別委員会」という諮問機関を設置した。
だが、この特別委員会も「情報を集約し提供する」という事の本質的な注意点についてはまったく考慮せずに「会員のために情報を集約し提供することはいいサービスだ」という点のみで安易に考えていたので、委員だった私は、会長の意向に思いっきり冷水をぶっ掛ける行為としてその他の諮問事項もあわせ個人的見解を出して真っ向否定したという事実があったりする。
今回、参考までに書いた個人的見解から情報集約についての危険性などについてまとめた部分を抜粋してアップしておく。
抜粋:「情報ソースを一本に絞ることの危険性について」
http://www.aa.alles.or.jp/~g-lawyer/column/2008.html
なんのために創業したのですか? ― 2008年01月10日 18時42分37秒
学研の地球儀から台湾が消えた? 中国が圧力「島」に変更
1月10日10時59分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080110-00000925-san-soci
「学研」(東京都大田区)グループが国内向けに販売した音声ガイド付きの地球儀が、中国政府からの圧力で台湾を単なる「台湾島」と表記していたという事件。
この中国の行為を「圧力であり問題だ」と考える人がいるかもしれないが、私からすれば文句を言う方が筋違い。
至極『当たり前』の事だと思う。
台湾の扱いについて言えば、中華人民共和国が昔から「自国の領土」と主張している事は国際関係を知る者からすれば誰もが知る事実だし、台湾が「国家」としてはまだ正式に認められていないという事も事実だ。
この状況で「中国内部」で製品を作っている以上、中国政府が「適正な表示を行うこと」と要求してきても拒否する権利自体、本来、学研側に存在しない。
これを「変だ」という人は、ローカルルールの原則を理解していないのだろう。
なぜなら、この件は見方を変えれば次のような状況を想定する事にもなるからだ。
例えば、日本国内でアメリカや他国の正式ライセンス生産で「核兵器」を製造したとする。
当然、日本国としては「非核3原則」に基づいて「核兵器の製造」をその業者に対し要求するだろうし、国外への搬出を抑えようとするだろう。
一方、生産する企業からすれば「依頼した国からの正式なライセンスがある以上、作る権利がある。日本の法や主張は適用できないはずだ」と主張するだろう。
この時「使われるのは日本以外の国だから別に作られせても構わない」と、企業活動の正当性を認めるだろうか?
当然、このような主張は認められない事が、理解できるだろう。
それぞれの国にはそれぞれの法や社会理念があり、その国で活動する場合、活動する国の法に従わなければならないというのは、国際的理念上の常識だ。
したがって今回の一件も、その生産場所が中国国内である限り、中国の権利義務に従うのは当然であって、中国の主張が正しい。
さて、ではこの問題はどこにあるのだろうか?
私は「学研」が安易に「コスト削減」に走ったことに問題の本質があると考えている。
「安く生産できるから中国で」とコスト削減を考えることは、企業としては当然の事だと思う。しかし「コストを削減するため」といって欠陥商品を作って流通させても構わないという事はない。
適当にでたらめな名前を書いた地球儀を「形があっているから別にいい」と販売した「おもちゃ」ならまだしも、このレベルでの地球儀ともなれば、日本国の地球儀として販売する以上、ここで書かれている地図内表記は「日本国ではこのように地名を認識している」として取り扱われるのが基本だ。
にも関わらず、間違った地名などを教えることは、地図や地球儀製作会社としての社会的責任や製品に対する責任を全く無視したものだとしかいえない。
これを「別紙で訂正メモを入れてあるからいいや」と考えるのは、明らかに製作企業としての考え方に問題がある。
『荒廃した日本を再建するには、次代を担う子どもたちの教育が最も大切だ』
学研トップメッセージ 代表取締役社長 遠藤 洋一郎 より抜粋
これが学研の基本理念のはずなのだが、その裏で、
『安く教材が作れるならば、教育も適当に間違った事を教えてもいい』
と考えていた学研グループ。
この考え方は教育産業企業として非常に問題があるのではないだろうか。
だが一方、これは学研だけの問題なのだろうか。
今、日本の企業のほとんどが「利益があがれば、自社の企業理念そのものを踏みにじってても構わない」と考えているのではないだろうか。
企業だけでなく、人の間にも「自分が経済的に得ならば、理念その他など『金にならないもの』は踏みにじっても構わない」。そんな風潮が蔓延していないだろうか。
そんな事はない。という人もいると思う。
だが、そのような人々に聞いてみたいと思う事がある。
「あなたの会社の理念はなんですか?」
「あなたの仕事は会社の理念を守っていますか?」
「あなたの理念はなんですか?」
1月10日10時59分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080110-00000925-san-soci
「学研」(東京都大田区)グループが国内向けに販売した音声ガイド付きの地球儀が、中国政府からの圧力で台湾を単なる「台湾島」と表記していたという事件。
この中国の行為を「圧力であり問題だ」と考える人がいるかもしれないが、私からすれば文句を言う方が筋違い。
至極『当たり前』の事だと思う。
台湾の扱いについて言えば、中華人民共和国が昔から「自国の領土」と主張している事は国際関係を知る者からすれば誰もが知る事実だし、台湾が「国家」としてはまだ正式に認められていないという事も事実だ。
この状況で「中国内部」で製品を作っている以上、中国政府が「適正な表示を行うこと」と要求してきても拒否する権利自体、本来、学研側に存在しない。
これを「変だ」という人は、ローカルルールの原則を理解していないのだろう。
なぜなら、この件は見方を変えれば次のような状況を想定する事にもなるからだ。
例えば、日本国内でアメリカや他国の正式ライセンス生産で「核兵器」を製造したとする。
当然、日本国としては「非核3原則」に基づいて「核兵器の製造」をその業者に対し要求するだろうし、国外への搬出を抑えようとするだろう。
一方、生産する企業からすれば「依頼した国からの正式なライセンスがある以上、作る権利がある。日本の法や主張は適用できないはずだ」と主張するだろう。
この時「使われるのは日本以外の国だから別に作られせても構わない」と、企業活動の正当性を認めるだろうか?
当然、このような主張は認められない事が、理解できるだろう。
それぞれの国にはそれぞれの法や社会理念があり、その国で活動する場合、活動する国の法に従わなければならないというのは、国際的理念上の常識だ。
したがって今回の一件も、その生産場所が中国国内である限り、中国の権利義務に従うのは当然であって、中国の主張が正しい。
さて、ではこの問題はどこにあるのだろうか?
私は「学研」が安易に「コスト削減」に走ったことに問題の本質があると考えている。
「安く生産できるから中国で」とコスト削減を考えることは、企業としては当然の事だと思う。しかし「コストを削減するため」といって欠陥商品を作って流通させても構わないという事はない。
適当にでたらめな名前を書いた地球儀を「形があっているから別にいい」と販売した「おもちゃ」ならまだしも、このレベルでの地球儀ともなれば、日本国の地球儀として販売する以上、ここで書かれている地図内表記は「日本国ではこのように地名を認識している」として取り扱われるのが基本だ。
にも関わらず、間違った地名などを教えることは、地図や地球儀製作会社としての社会的責任や製品に対する責任を全く無視したものだとしかいえない。
これを「別紙で訂正メモを入れてあるからいいや」と考えるのは、明らかに製作企業としての考え方に問題がある。
『荒廃した日本を再建するには、次代を担う子どもたちの教育が最も大切だ』
学研トップメッセージ 代表取締役社長 遠藤 洋一郎 より抜粋
これが学研の基本理念のはずなのだが、その裏で、
『安く教材が作れるならば、教育も適当に間違った事を教えてもいい』
と考えていた学研グループ。
この考え方は教育産業企業として非常に問題があるのではないだろうか。
だが一方、これは学研だけの問題なのだろうか。
今、日本の企業のほとんどが「利益があがれば、自社の企業理念そのものを踏みにじってても構わない」と考えているのではないだろうか。
企業だけでなく、人の間にも「自分が経済的に得ならば、理念その他など『金にならないもの』は踏みにじっても構わない」。そんな風潮が蔓延していないだろうか。
そんな事はない。という人もいると思う。
だが、そのような人々に聞いてみたいと思う事がある。
「あなたの会社の理念はなんですか?」
「あなたの仕事は会社の理念を守っていますか?」
「あなたの理念はなんですか?」
菅はやっぱり馬鹿なのか? ― 2008年01月10日 21時43分24秒
※ 訂正 「参議院で民主党の対案が通らなかった」という意味で記事を書きましたが「参議院外交防衛委員会」で通らなかったの間違いでした
一応、「本会議ではぎりぎり通過した」ことをあわせて掲載します。
(とはいえ、あまり意味は変わりませんが) 1/12
--------
新テロ法案、11日に衆院再議決で成立へ
1月10日20時40分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080110-00000972-san-pol
臨時国会の会期末を15日に控え参院外交防衛委員会は10日、インド洋で海上自衛隊の補給活動を再開するための新テロ対策特別措置法案を民主、共産、社民各党の反対多数で否決した。法案は11日午前の参院本会議で否決される見通し。
(略)
これとは別に、参院外交防衛委は、民主党が対案として提出した「国際テロリズム防止と根絶のためのアフガニスタン復興支援特別措置法案」も採決し、自民、公明、共産、社民各党の反対多数で否決した。この法案も衆院に返付されるが、審議未了で廃案となる。
他
<新テロ法案>衆院再可決で成立へ 2月中旬活動再開目指す
1月10日21時18分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080110-00000134-mai-pol
------------
NHKのニュースで菅直人さんが、今日のテロ対策法案否決をうけ「一院で否決された以上、その重さを考えるべきだ」と言っていた。
が、ちょっと待って欲しい。
同時に出した「民主党側のテロ対策法案」(「国際テロリズム防止と根絶のためのアフガニスタン復興支援特別措置法案」)が参議院で否決された事について、民主党自身はその重さをどう考えているのだろうか?
参議院では、民主党が与党であったはずだ。
その優位性があるにも関わらず「テロ対策法案(民主党案)が通らなかった」
この方が問題じゃないだろうか。
今後、仮に「参議院で法案が否決された責任」として福田総理の問責決議案を出すというならば、それ以上に「参議院第一党の民主党案が否決された責任」を小沢代表も取らなくてはおかしくはないだろうか。
そもそも参議院「与党」でありながら、その参議院で否決されるような法案しか出せないという事自体、民主党の政権能力・法案立案能力の低さが露呈していると思う。
テロ対策法案をただひたすら反対。
だけど、対案として出した法案は、どうにもならない屑法案。
自分が優位であるにも関わらず法案を通すこともできない政権運営能力。
こんな状況で民主党を信じられる人は、いったい何を考えているのだろう。
自民党が、ある意味「腐敗した政党」というのは正しいかもしれない。
だけど2大政党を標榜する民主党は、そんな自民党に能力面で遠く遥かに及ばない「万年野党」のままでしかない。
2大政党の受け皿となるべき民主党は、人材不足というよりも「政権能力・立案能力」自体が未だにない。
結局、民主党は自民党以上に『どうしようもない政党』ということを自ら証明してしまったと思う。
これは「自分達に法案立案能力がない」という事なのだから、自民党との政権争い以前の問題だ。
これを「今までは機会がなかったから」という事で擁護する人もいるかもしれない。だけど、その考えは大きく間違っているという事ができる。
民主党は元々イギリスを見習って「影の内閣」を党内に持ち、『いつでも交代できる準備はできている』と標榜していたはずだ。
にも関わらずこの体たらく。
民主党は、今まで何をやっていたのだろう。
今まで一生懸命アピールしていた「いつでも政権担当できます」という言葉は何だったのだろう。
このような状況での「政権交代」は非常に問題があると思う。
今まで何度もこのブログで書いているが、私は「民主党が嫌い」というわけではない。
実際、県議会議員や市議会議員に何人も知り合いはいるし、一応、友人といえる間柄かもしれない。
また、その縁を通じて何度か国会議員の方の意見を聞く機会もあった。
(菅直人さんや河村たかしさんと一緒の飲み会で呑んだ事もあった)
それでも、私には「民主党に政権担当能力がある」と言うことだけはできない。
今日のように「今までやってきた事」が自ら無能だと証明してしまっているから。
だから『「政権担当政党」は「自民党」であるべきだ』と言わざるを得ないのだ。
好きか嫌いかではなく、腐っているかどうかではなく、まず「能力があるかどうか」が大前提なのだから。
一応、「本会議ではぎりぎり通過した」ことをあわせて掲載します。
(とはいえ、あまり意味は変わりませんが) 1/12
--------
新テロ法案、11日に衆院再議決で成立へ
1月10日20時40分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080110-00000972-san-pol
臨時国会の会期末を15日に控え参院外交防衛委員会は10日、インド洋で海上自衛隊の補給活動を再開するための新テロ対策特別措置法案を民主、共産、社民各党の反対多数で否決した。法案は11日午前の参院本会議で否決される見通し。
(略)
これとは別に、参院外交防衛委は、民主党が対案として提出した「国際テロリズム防止と根絶のためのアフガニスタン復興支援特別措置法案」も採決し、自民、公明、共産、社民各党の反対多数で否決した。この法案も衆院に返付されるが、審議未了で廃案となる。
他
<新テロ法案>衆院再可決で成立へ 2月中旬活動再開目指す
1月10日21時18分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080110-00000134-mai-pol
------------
NHKのニュースで菅直人さんが、今日のテロ対策法案否決をうけ「一院で否決された以上、その重さを考えるべきだ」と言っていた。
が、ちょっと待って欲しい。
同時に出した「民主党側のテロ対策法案」(「国際テロリズム防止と根絶のためのアフガニスタン復興支援特別措置法案」)が参議院で否決された事について、民主党自身はその重さをどう考えているのだろうか?
参議院では、民主党が与党であったはずだ。
その優位性があるにも関わらず「テロ対策法案(民主党案)が通らなかった」
この方が問題じゃないだろうか。
今後、仮に「参議院で法案が否決された責任」として福田総理の問責決議案を出すというならば、それ以上に「参議院第一党の民主党案が否決された責任」を小沢代表も取らなくてはおかしくはないだろうか。
そもそも参議院「与党」でありながら、その参議院で否決されるような法案しか出せないという事自体、民主党の政権能力・法案立案能力の低さが露呈していると思う。
テロ対策法案をただひたすら反対。
だけど、対案として出した法案は、どうにもならない屑法案。
自分が優位であるにも関わらず法案を通すこともできない政権運営能力。
こんな状況で民主党を信じられる人は、いったい何を考えているのだろう。
自民党が、ある意味「腐敗した政党」というのは正しいかもしれない。
だけど2大政党を標榜する民主党は、そんな自民党に能力面で遠く遥かに及ばない「万年野党」のままでしかない。
2大政党の受け皿となるべき民主党は、人材不足というよりも「政権能力・立案能力」自体が未だにない。
結局、民主党は自民党以上に『どうしようもない政党』ということを自ら証明してしまったと思う。
これは「自分達に法案立案能力がない」という事なのだから、自民党との政権争い以前の問題だ。
これを「今までは機会がなかったから」という事で擁護する人もいるかもしれない。だけど、その考えは大きく間違っているという事ができる。
民主党は元々イギリスを見習って「影の内閣」を党内に持ち、『いつでも交代できる準備はできている』と標榜していたはずだ。
にも関わらずこの体たらく。
民主党は、今まで何をやっていたのだろう。
今まで一生懸命アピールしていた「いつでも政権担当できます」という言葉は何だったのだろう。
このような状況での「政権交代」は非常に問題があると思う。
今まで何度もこのブログで書いているが、私は「民主党が嫌い」というわけではない。
実際、県議会議員や市議会議員に何人も知り合いはいるし、一応、友人といえる間柄かもしれない。
また、その縁を通じて何度か国会議員の方の意見を聞く機会もあった。
(菅直人さんや河村たかしさんと一緒の飲み会で呑んだ事もあった)
それでも、私には「民主党に政権担当能力がある」と言うことだけはできない。
今日のように「今までやってきた事」が自ら無能だと証明してしまっているから。
だから『「政権担当政党」は「自民党」であるべきだ』と言わざるを得ないのだ。
好きか嫌いかではなく、腐っているかどうかではなく、まず「能力があるかどうか」が大前提なのだから。
なんで中国相手だと、事実を見ずに感情で話すのか? ― 2008年01月11日 16時51分51秒
昨日の続き
中国外務省「国内法順守せよ」 地球儀の台湾表記で見解
1月11日8時2分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080111-00000075-san-int
- 同報道官は、「(中略)中国で業務に従事する外国企業は中国の関係法律・法規を順守しなくてはならない」と述べた。 -
主張する国が好きか嫌いかという感情論でなく、世界におけるルールとして「正当かどうか?」という点で言えば、この記事で出ている報道官のコメントが極めて正しいと思います。
中国や日本の政府がどうこうという問題でなく「その地で活動する以上、その地のルールに従う」これがなによりも絶対原則。
これを無視して行動することは『国家主権』そのものを否定することになります。
単純に「中国批判」をしている人が多すぎますが、「国家主権」(その国のルールに従う事)を認めないというならば、「日本国内で他国の人間が本国ルールで活動する事」も容認しなければならないはずです。
安易に「中国に日本企業の活動を云々されるいわれはない」というならば、アメリカ人やイギリス人、また中国人やアジアの人々が日本で日本のルールを無視する事も容認しください。
感情論だけでモノを語り、事実から目をそらすのはいい加減やめにしませんか?
-----
「台湾島」と表記の地球儀、学研が販売中止
1月11日4時56分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080110-00000984-san-soci
こちらも「当り前」。
地図において表記が間違っているというのは明らかに「欠陥」
しかも「過失」によるものならばまだいいが、今回は明らかに「故意」(間違っている事を判った上で生産した)による欠陥。
販売を中止することに対して色々言っている人がいますが、
これは「状況の問題」ではありません。
「判っていて欠陥商品を製作・販売した」
学研の姿勢そのものが問題です。
ですから、回収・販売中止する事が当たり前で、
その事を批判する人の方が、問題の本質を考えず単に「隣国が嫌い」という感情論で話をしていて、問題なのではないでしょうか。
(中国が文句を言ってきたから)
『適当に欠陥製品を作って』
『メモを書いて、ごまかしたから、欠陥があっても売っていいや」
この学研の考え方に文句を付けず、文句を言ってきた中国だけを批判する。
そんな人の思考が私には理解できません。
---
…中国という国をどう思われるか? と訊かれれば、
今の中国政府は「嫌い」ですし「信用できない国」とは答えますが、
それと
『だから国際ルールの基本を無視してもいい』という事が正当化できるかどうかと言えば、それは『まったくの別問題』です。
-----
何度も言い方を変えて言いますが、
今回の問題は、今までの教科書問題などのような
「中国の、日本に対する内政干渉」ではありません。
あくまで「中国の、国内で活動する企業に対する『国内問題』です」
これを不当な圧力や「日本に対する内政干渉」と考える事自体、(中国が相手だから)と「本質を無視している」といえます。
(というか、「中国国内で『中国の認識に反した製品』を『外国企業の論理』により生産する事を認めさせる」考え方の方が、中国に対する「内政干渉」にあたるのですが)
------
「台湾島」と表記の地球儀、学研が販売中止 --- 国際ビジネス感覚の欠如が引き起こした問題
http://blogs.yahoo.co.jp/cosmosfish/20241725.html
私よりもしっかりとグローバルという事についてかいてあるサイト
……ちなみに、「学研が持つ中国の工場」と私も勘違いしていたのだけど、正確には「生産を委託された「中国企業」の工場」だったのね。
そりゃ、もっと中国側の主張が正しいじゃん。
しかも「メイド・イン・チャイナ」だし。
中国外務省「国内法順守せよ」 地球儀の台湾表記で見解
1月11日8時2分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080111-00000075-san-int
- 同報道官は、「(中略)中国で業務に従事する外国企業は中国の関係法律・法規を順守しなくてはならない」と述べた。 -
主張する国が好きか嫌いかという感情論でなく、世界におけるルールとして「正当かどうか?」という点で言えば、この記事で出ている報道官のコメントが極めて正しいと思います。
中国や日本の政府がどうこうという問題でなく「その地で活動する以上、その地のルールに従う」これがなによりも絶対原則。
これを無視して行動することは『国家主権』そのものを否定することになります。
単純に「中国批判」をしている人が多すぎますが、「国家主権」(その国のルールに従う事)を認めないというならば、「日本国内で他国の人間が本国ルールで活動する事」も容認しなければならないはずです。
安易に「中国に日本企業の活動を云々されるいわれはない」というならば、アメリカ人やイギリス人、また中国人やアジアの人々が日本で日本のルールを無視する事も容認しください。
感情論だけでモノを語り、事実から目をそらすのはいい加減やめにしませんか?
-----
「台湾島」と表記の地球儀、学研が販売中止
1月11日4時56分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080110-00000984-san-soci
こちらも「当り前」。
地図において表記が間違っているというのは明らかに「欠陥」
しかも「過失」によるものならばまだいいが、今回は明らかに「故意」(間違っている事を判った上で生産した)による欠陥。
販売を中止することに対して色々言っている人がいますが、
これは「状況の問題」ではありません。
「判っていて欠陥商品を製作・販売した」
学研の姿勢そのものが問題です。
ですから、回収・販売中止する事が当たり前で、
その事を批判する人の方が、問題の本質を考えず単に「隣国が嫌い」という感情論で話をしていて、問題なのではないでしょうか。
(中国が文句を言ってきたから)
『適当に欠陥製品を作って』
『メモを書いて、ごまかしたから、欠陥があっても売っていいや」
この学研の考え方に文句を付けず、文句を言ってきた中国だけを批判する。
そんな人の思考が私には理解できません。
---
…中国という国をどう思われるか? と訊かれれば、
今の中国政府は「嫌い」ですし「信用できない国」とは答えますが、
それと
『だから国際ルールの基本を無視してもいい』という事が正当化できるかどうかと言えば、それは『まったくの別問題』です。
-----
何度も言い方を変えて言いますが、
今回の問題は、今までの教科書問題などのような
「中国の、日本に対する内政干渉」ではありません。
あくまで「中国の、国内で活動する企業に対する『国内問題』です」
これを不当な圧力や「日本に対する内政干渉」と考える事自体、(中国が相手だから)と「本質を無視している」といえます。
(というか、「中国国内で『中国の認識に反した製品』を『外国企業の論理』により生産する事を認めさせる」考え方の方が、中国に対する「内政干渉」にあたるのですが)
------
「台湾島」と表記の地球儀、学研が販売中止 --- 国際ビジネス感覚の欠如が引き起こした問題
http://blogs.yahoo.co.jp/cosmosfish/20241725.html
私よりもしっかりとグローバルという事についてかいてあるサイト
……ちなみに、「学研が持つ中国の工場」と私も勘違いしていたのだけど、正確には「生産を委託された「中国企業」の工場」だったのね。
そりゃ、もっと中国側の主張が正しいじゃん。
しかも「メイド・イン・チャイナ」だし。
この記事を多くの人に読んでもらいたい!!そう思ったら『人気ブログランキング』押してください
最近のコメント